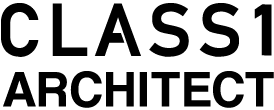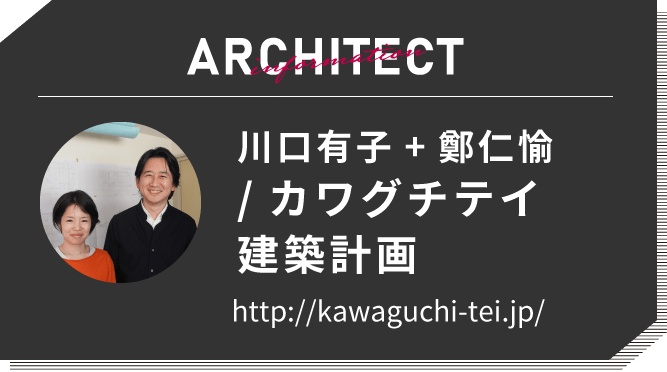住民の生活に溶け込む秘密は「繋がっている」感覚。
カワグチテイ建築計画がつくる「余白」の意味に迫る。
CLASS1 ARCHITECT Vol.06で特集した、「美波町医療保健センター」と「市原湖畔美術館」。どちらも、利用者の「余白」となるような建築であることが本誌から読み取れる。今回の会員限定記事では、これらの設計を手掛けたカワグチテイ建築計画の川口有子氏、鄭仁愉氏へのインタビューの中で、誌面に掲載できなかった話をいくつか紹介したい。特に「市原湖畔美術館」について注目し、彼らの建築のテーマである「余白」という、やや抽象的な概念をもう少し掘り下げてみたいと思う。
LIMITED STORY #01
あらゆる人や目的に開かれていく、自由度の高い美術館に。
本誌を見てもわかるように、「市原湖畔美術館」は非常に豊かな自然に囲まれている。川口氏によれば、特に「芝生広場」は水に面しており緑が広がる魅力的な場所だったため、あらゆる人が自由に入ることができるように工夫したという。以前は入館料がないと芝生広場には入れないつくりだったが、元の入口を搬入口とし、広場側をエントランスにしたことで、誰でもアクセスできるようになった。
広場にカフェも併設したことで「美術館には行かないが広場には行く」という人も多くいる。カフェで提供しているピザは美味しいと評判で、車でしか来られない場所であるにもかかわらず、ピザを求めて地元民も含め客が多く訪れるという。他にも、たまたま通りかかり遊んで帰る家族もいれば、ピクニックをする者もいれば、釣りをする者もいる。
凄く開かれた場所になったと思います。元々、ご飯を食べたり、ピクニックしたりといった活動のひとつとして美術作品と出合えるような場所にしたいなと思って設計したので、ここに訪れたときに思い描いた光景に出合えると嬉しく思います。(鄭氏)
「芝生広場」をはじめとする美術館を囲む環境が、使い方を限定しない「余白」として多くの人々を招き入れている。「市原湖畔美術館」はある意味、美術館らしくない場所として愛されているのだ。
そして美術館の内部もまた、自由度の高い空間になっている。展示室では、展示をするアーティストが空間自体をその都度ガラリと変えていく。美術館を訪れるたびに、その内観は大胆にリノベーションをしたかのように生まれ変わる。ふたりはこの美術館の内部に関しても、「余白」について語っていた。
この建物の中も大きな余白みたいなものですよね。役割が決まった場所は事務室くらい。『いつもよくわからない場所で、よくわからないけど何か面白いことが行われている』ような感じが、僕は気に入っています。(鄭氏)
LIMITED STORY #02
建築と「余白」の関係
このように、カワグチテイ建築計画が手掛ける建築において、「余白」というキーワードは印象に残る。実際、川口氏と鄭氏も「余白を残す建築」は普段意識していることだと語っていた。
機能が一対一にあるというよりは、ずるずるっと繋がってるものが好きで。良くいえば繋がっているし、悪くいえばだらしないのかもしれない。(鄭氏)
その意識の根底にあるのは、「空間の使い方は時代によって変わる」という考え方。時代とともに変わる用途に合わせるように、意味も在り方も変わり、使われ続ける。何かのためにつくられた建築ではなく、常にその場所にある、環境の一部のような建築をふたりは目指している。川口氏は「私たちが設計したものもいつかは違う形に変わっていく必要があると思うし、それを想像したり見届けたりするのが私たちの楽しみでもある」と穏やかに話していた。
カワグチテイ建築計画の考える「余白」とは、ただ単に物理的なスペースや広さを与えることではない。それだけでなく、空間の変化を楽しむ気持ちや、利用者自身が建物の在り方を決められる、主体性への期待といったものを「余白」としているのではないだろうか。彼らが手掛ける建築は、「なんでもないからこそ、なんでもできる場所」をつくる建築の余白の価値を考えるきっかけを与えてくれる。